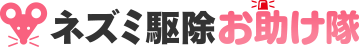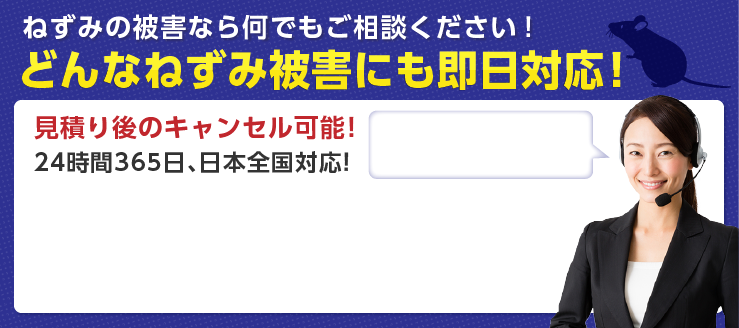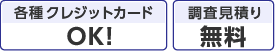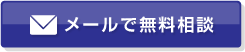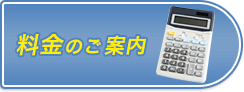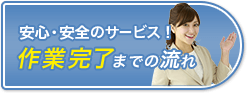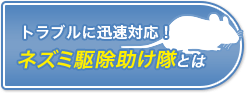ねずみが巣を作りやすい場所とは?撤去方法や注意点などを解説します

ねずみがいるかもしれないと思ったときは、早めに天井裏や押し入れの奥などを確認するようにしましょう。もしかしたら、ねずみに巣を作られているかもしれないからです。巣があった場合は、繁殖する前に撤去することで被害がひどくなる前に防ぐことができるでしょう。
このコラムでは、ねずみが巣を作りやすい場所や巣の撤去方法について解説していきます。巣の位置によっては、自力で撤去するのが難しい場合もあります。そのときは、無理せず業者に依頼するようにしましょう。
ねずみがいると感じたときに確認する場所
家にねずみが侵入し巣を作られてしまうと、ねずみが繁殖し駆除するのが難しくなってしまいます。そうなってしまう前に、ねずみの有無も含め巣を作られていないかチェックしていきましょう。
家のなかで巣を作られやすい場所

ねずみはおもに以下のような場所に巣を作ることが多いです。
- 天井裏や屋根裏
- 押し入れ
- 天袋
- 壁の内部
- 床下
- 冷蔵庫など家具の裏や隙間
- 物置や倉庫
ねずみや巣を目視できても、場所が狭く体が入らない場合は自力での対処が困難になります。そのときは、無理をせずできるだけ早く業者に連絡し対処してもらいましょう。
巣を作られやすい理由
ねずみが家に巣を作る理由には、以下のことがあげられます。
■エサがある
生ゴミや家に置いてある食品はねずみのエサになってしまうため、何も対策をしていないと住みつかれる原因となります。
■外敵がいない
ねずみにとって外は危険と隣り合わせの世界です。しかし人の家のなかは、ねずみを脅かす敵はいないため安心できる場所となります。
■巣を作るのに必要な材料がある
ねずみは、段ボールやティッシュペーパーなどを材料にして巣を作ることがあるのです。ほかにも古着や布の切れ端なども巣の材料となります。これらを放置していると巣を作られてしまう可能性があります。
■暖かい場所である
ねずみは寒さに弱いため、冬の時期になると家に侵入することが多くなります。そして、ねずみは巣作りする場所を決め、必要な材料を調達し巣を完成させて繁殖してしまう可能性が高いです。
ラットサインでねずみと判断することもできる
家のなかに糞尿やかじられた跡、黒い汚れなどのラットサインがあるかを確認しましょう。ラットサインがあれば、ねずみが侵入していると考えられます。ラットサインが数ヶ所で見られたり同じ場所に頻繁にあったりするようなら、巣を作られているおそれもあります。そうであれば、繁殖して増える前に駆除して巣を撤去しなくてはいけません。
しかし、ねずみの駆除や巣の撤去に抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、無理に駆除や撤去作業をせず業者に相談することをおすすめします。業者に依頼することで、ねずみを見ることもありませんし、駆除後の処理までおこなってもらえるからです。
弊社にお電話いただければ、ご要望にあった業者をご紹介することが可能です。もちろん、ご相談だけしたいという方でもご利用できますので、お気軽にご連絡ください。
種類によって巣を作る場所は異なる
ねずみの巣の場所によって、家に侵入している種類を判断することが可能です。ここでは、家のなかに侵入することが多い「クマネズミ」「ハツカネズミ」「ドブネズミ」の3種類がどこに巣を作るかをご紹介します。
クマネズミ

クマネズミは高い場所や、人目につかない場所などに巣を作ります。
■場所
- 屋根裏や天井裏
- 押し入れ
- 天袋内
- 壁の内部
クマネズミは、布のほかに布団の綿や断熱材も巣の材料にしてしまいます。布団や断熱材にかじられた跡がある場合は、クマネズミと考えてよいかもしれません。
ハツカネズミ
ハツカネズミは以下の場所で巣を作ります。
■場所
- 物置や倉庫
ハツカネズミは体が小さく狭い場所を好むため、物がたくさんあって死角の多い物置などに巣を作ることが多いです。また、家のなかであれば、家具の隙間などに巣を作ることがあります。
ドブネズミ
ドブネズミはクマネズミやハツカネズミとは違い、湿気のある場所に巣を作ります。
■場所
- 冷蔵庫の裏
- 食器棚の後ろ側
- 床下
湿気がある場所でねずみを見かける場合は、ドブネズミと判断してよいでしょう。
巣の撤去方法と予防対策
ねずみの巣だとわかったら、繁殖するのを防ぐために巣を撤去しましょう。ここでは、ご自身で巣を撤去する方法をご説明していきます。撤去作業の際に注意することや、予防対策についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
巣の撤去を始める前に

撤去をおこなう前に、準備するものや注意点を確認しておきましょう。
■準備するもの
- マスク
- ゴム手袋
- 帽子
- ほうき
- ちりとり
- ビニール袋
上記のものが必要になる理由は、注意点でご説明します。
■撤去する際の注意点
巣を撤去する際は、絶対に素手で作業をおこなわないでください。ねずみの体にはダニやノミがおり、また糞尿には、腹痛や高熱などを引き起こすサルモネラ菌などの病原菌が含まれています。そのため、ゴム手袋やマスクなどを着用し、作業をおこなうようにしましょう。
もし巣にねずみがいた場合、種類によっては咬みついてくることがあります。ねずみに咬まれてしまうと、発熱や頭痛などを引き起こす「鼠咬症(そこうしょう)」に感染するおそれがあり、とても危険です。
このようなリスクを避けるために、ねずみがいた場合は無理に撤去作業をおこなわず業者に相談しましょう。
撤去の手順
必要な道具の準備ができ、ゴム手袋などを着用したら巣の撤去を始めます。手順は以下のとおりです。
■作業手順
- ほうきとちりとりで巣を取り除く(このとき糞も取り除くようにする)
- 取り除いた巣をビニール袋に入れて口を結び、すぐに処分する
- ねずみの巣や糞を取り除いたあと、菌をなくすため広範囲に消毒用のアルコールスプレーなどを吹きかけ殺菌消毒をおこなう
- 作業時に着ていた衣類はすぐに着替えて洗濯をする(作業の際に菌などが付着している恐れがあるため)
ねずみの死骸があった場合は、新聞紙に包んでからビニール袋に入れて処分し、死骸のあった場所は殺菌消毒をおこないましょう。
再発させないために予防対策をしよう
巣の撤去が完了したら、再び巣を作られないように対策をおこないましょう。
■食品はプラスチック容器などに入れて保管する
ねずみはエサが豊富にある場所に寄り付きやすくなります。ねずみに食品を食べられてしまわないために、フタが付いている容器に移し替えて保管しましょう。
また、生ゴミがあってもねずみは寄ってきてしまいます。生ゴミを捨てる際は、フタ付きのゴミ箱に入れてねずみに侵入されないようにしておきましょう。ゴミ箱の周囲にねずみが嫌うニオイがするもの(ハッカやペパーミントなど)をスプレーしておくのも効果的です。
■巣の材料になる段ボールや新聞紙などを処分する
前述したように、段ボールや新聞紙などはねずみの巣の材料にされてしまいます。そのため、必要なくなった段ボールなどはとっておかず、処分するようにしましょう。また、服やタオルなどの布類やビニールなども巣の材料となってしまいます。
まだ使用する布類は、プラスチック製のフタ付き収納ケースへ収納します。タンスに収納する場合は、隙間を作らないようにしっかり締めておきましょう。
■ねずみの侵入口になる場所を塞ぐ
ねずみは小さな隙間があれば、歯でかじって隙間を広げて侵入してきます。そのため、ねずみが侵入してきそうな隙間を見つけた際は、防鼠効果のあるパテを使って隙間を埋めましょう。
また、防鼠用の金網や金属タワシなどでも隙間を塞ぐことも可能です。パテや金網などは、ホームセンターやネット通販で購入できます。
業者に依頼することも検討しよう
ねずみの巣の撤去作業は病原菌を吸い込んだり、ダニなどが肌に触れたりしないように対策しなくてはいけません。また、巣のあった場所をきれいに掃除し殺菌消毒をおこなう必要もあります。
これらの作業に慣れていないと、時間がかかってしまいますし、しっかり殺菌消毒ができていないと病原菌に感染してしまうおそれもあるのです。また、ねずみに咬まれる危険性もあります。そういった可能性を減らすために、ねずみの習性を理解し、駆除をおこなってきた業者に依頼することをおすすめします。
業者をお探しの際は、ぜひ弊社をご利用ください。ご連絡をいただければ、全国にある弊社加盟店をご紹介させていただきます。業者による現地見積りやお見積りは無料となっておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。
【記載情報はコンテンツ作成時の情報です】
ネズミ駆除の関連記事
- ねずみを家から追い出す方法!【忌避剤】の種類や使い方をご紹介
- ネズミの好物とは?意外なものまで食べてしまうネズミの実態について
- ねずみのフン尿は放置厳禁!安全に掃除する手順をお教えします
- ねずみの臭い被害!死骸やフン尿を除去して再発を防ぐ対策を
- ねずみを唐辛子で駆除?人体に影響が少ない駆除や業者依頼もご紹介
- ねずみが一番出る時期は秋冬!その理由・習性と予防や駆除方法を解説
- ねずみは夜行性とはかぎらない?昼間に行動するねずみは注意が必要!
- ねずみの出る家の特徴を知って被害に遭わないようにしておこう!
- エアコンのなかにねずみがいる!追い出す方法と侵入されない対策方法
- ねずみ被害で怖いのは食害だけじゃない!被害例や予防対策などを解説